-

出版研究55
¥2,860
発売:2025年5月 出版に関する事項の調査、研究活動を行う日本出版学会の会員による、出版・情報・メディアなど多様な分野の研究論文や有識者の座談会を掲載。 目次 特集1 日本出版学会 創立55周年記念講演会 概要 韓国の出版・書店支援政策と書店ビジネスモデルの革新 白 源根 ジャンプ・マンガのデジタル化の歩みと海外への挑戦 細野修平 特集2 第21回 国際出版研究フォーラム 概要 デジタルアーカイブ時代のエディトリアルとは ――人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)とジャパンナレッジの共同プロジェクトを手がかりに 鈴木親彦,山崎隆広 出版学における木版口絵研究のためのデジタルアーカイブデザイン 常木佳奈 角筆から考える角筆文献についての一考察 ――角筆文献調査から考える 近藤友子 「読書バリアフリー法」制定後の成果と課題 ――出版界の取組みを中心に 野口武悟 ■ 論文 出版史から見た坪谷善四郎 ――新潟県加茂市立図書館所蔵資料の分析から 長尾宗典 美容整形広告から見る韓国男性の男らしさ ――ミリタリー雑誌からの考察 小平沙紀 「オンナ・コドモ」のジャーナリズムとリスク・コミュニケーション ――女性週刊誌の子宮頸がんワクチン報道に注目して 本多祥大 ■ 研究ノート 「東京シティ情報誌」の現在地 ――映画館の変容と情報誌の関係 平松恵一郎 ■ レポート 「教養」(Bildung)の語史 ――明治~昭和前期の独和・和独辞典の検討 松井健人 日本出版学会 編集 発行元:日本出版学会 A5判 224ページ

-

アレッサンドロ・ヴァリニャーノ ― 日本に活字印刷を南蛮船でもたらした宣教師 ―
¥2,750
発行:2022年10月 天正遣欧少年使節派遣の計画・実施で知られるアレッサンドロ・ヴァリニャーノだが、活版印刷術をいち早く日本にもたらした人物であり、その成果としての『キリシタン版』は金属活字で印刷された出版物として日本の出版史上、貴重な存在である。 グーテンベルクの発明した活版印刷術をいち早く日本にもたらしたヴァリニャーノの足跡を詳細に語る。 目次 プロローグ 1 ちっちゃな騎士さま 2 メルチェリエ通りの書店で 3 つかの間の栄光と生涯の恥辱 4 司祭になり、東インド巡察師に 5 巡察の旅の最後が日本だった 6 まさにザビエルの三十年後だった 7 有馬でひらめいた「活字印刷」 8 日本最初のキリシタン大名 大村純忠 9 豊後で得たものは大きかった 10 信長に気に入られる 11 少年使節の計画をかためる 12 少年使節の船出 13 ゴアでの失意 14 国字活字に燭光 15 リスボンからの便り 16 ローマ教皇の謁見を受ける旅 17 リスボンでの印刷修行 18 日本人、コンスタンチノ・ドラード これを版に刻するものなり 19 日本最初の活字印刷所が加津佐に 21 日本最初の国字活字本『どちりいな・きりしたん』 22 加津佐から天草へ、そしてマカオ 23 三度目の日本で 24 晩年、そして、それから あとがき 参考年表 おもなキリシタン版 参考図書 青山敦夫 著 発行元:印刷学会出版部 四六判上製 258ページ
-

パブリッシング・スタディーズ
¥2,860
発行:2022年4月 各分野で活躍する、日本出版学会会員の知識を集結。出版史から制度、産業、書籍・雑誌・マンガ、デジタルコンテンツ、書店・読者までを概説する。「出版学」を学ぶ学生のテキストとして、また研究者を目指す人や出版業界の関係者が出版全体を通観するのに役立つ。 目次 序章 パブリッシング・スタディーズへの誘い 序.1 これまでの「出版」研究 序.1.1 第1期「出版学模索期」 序.1.2 第2期「出版研究確立期」 序.1.3 第3期「出版研究成熟期」 序.2 これからのパブリッシング・スタディーズ ─────────────────────────── 第1章 出版史 1.1 西洋出版略史 1.1.1 印刷と出版物の誕生 1.1.2 西洋における出版と社会 1.2 日本における出版の展開と社会 1.2.1 前近代 1.2.2 近代 1.3 印刷技術の発展と出版の高度化 1.3.1 活版技術の成立と発展 1.3.2 手動写植から電算写植へ 1.3.3 デジタルによる出版の発展と多様化 ─────────────────────────── 第2章 制度 2.1 出版の自由と法 2.1.1 表現の自由の概要 2.1.2 名誉毀損 2.1.3 プライバシー 2.1.4 性表現 2.1.5 営利的言論 2.1.6 知る権利 2.1.7 再販制 2.2 出版の自由とアカウンタビリティー・システム 2.2.1 ベルトランのMAS 2.2.2 日本の出版界のMAS 2.3 著作権 2.3.1 著作権法と出版 2.3.2 著作物 2.3.3 著作者 2.3.4 著作者の権利 2.3.5 権利制限規定 2.3.6 保護期間 2.3.7 権利侵害 ─────────────────────────── 第3章 産業 3.1 日本の出版産業の構造 3.1.1 日本の出版産業の足取り 3.1.2 日本の出版産業の規模と構成 3.1.3 本や雑誌が読者に届くまで 3.1.4 デジタルシフトによる編集と営業の連携強化 3.1.5 日本の出版産業の動向 3.2 流通 3.2.1 概要 3.2.2 取次 3.2.3 出版流通の歴史 3.2.4 流通制度・システムの問題点 3.2.5 出版流通改革の動き 3.2.6 流通構造の多様化へ 3.3 出版社の業務 3.3.1 「出版社」とは 3.3.2 出版メディア 3.3.3 出版社の仕事 3.3.4 出版を担う人材 ─────────────────────────── 第4章 書籍 4.1 歴史 4.1.1 近代 4.1.2 現代 4.2 文化と機能 4.2.1 書籍とは何か 4.2.2 書籍の機能とは何か 4.2.3 書籍の文化、書籍と文化 4.3 デジタル化と今後の展開 4.3.1 書籍のデジタル化とは何か? 4.3.2 書籍のデジタル化の現状 4.3.3 書籍のデジタル化の未来 ─────────────────────────── 第5章 雑誌 5.1 日本における雑誌の歴史 5.1.1 近代 5.1.2 現代 5.2 文化と機能 5.2.1 雑誌は文化をどう形成したか 5.2.2 雑誌の機能とは何か 5.3 デジタル化と今後の展開 5.3.1 デジタル雑誌の登場背景 5.3.2 現状と課題 5.3.3 雑誌の今後の展開 ─────────────────────────── 第6章 マンガ 6.1 歴史 6.1.1 はじめに 6.1.2 明治・大正・昭和初期(戦前) 6.1.3 1945~1970年代初頭:マス産業化への道のり 6.1.4 1970年代半ば~1990年代半ば:黄金時代 6.1.5 1996年~2000年代後半:停滞期 6.2 マンガ編集 6.2.1 編集という仕事 6.2.2 編集者の精神性──zealとmodesty 6.2.3 編集長の役割 6.3 電子コミック 6.3.1 電子コミックと物質性 6.3.2 電子コミック市場 6.3.3 電子コミックの利用 6.3.4 電子コミックの特徴と今後の展望 ─────────────────────────── 第7章 デジタル・コンテンツ 7.1 動画 7.1.1 動画の起源と機能 7.1.2 動画の文法 7.1.3 物語・報道情報の媒体としての動画 7.1.4 動画メディアの現状 7.1.5 動画メディアの問題点 7.1.6 動画メディアの将来像 7.2 文字 7.2.1 文字 7.2.2 電子書籍 7.2.3 デジタルコンテンツとビジネス 7.2.4 文字コンテンツの今後 7.3 音声 7.3.1 出版と「声の文化」 7.3.2 音声コンテンツの歴史 7.3.3 オーディオブック市場の現状 7.3.4 事例としてのAmazon Audible 7.3.5 「音声」コンテンツの展望と課題 7.3.6 「聴く読書」と読みの作法 ─────────────────────────── 第8章 読者へ届ける 8.1 書店 8.1.1 概況と歴史 8.1.2 読書装置としての書店 8.1.3 出版不況後の書店業界の動きと展望 8.2 図書館 8.2.1 図書館の種類 8.2.2 図書館の社会的意義と機能 8.2.3 図書館のサービス 8.2.4 出版と図書館の関係 8.2.5 電子図書館の登場と普及 8.2.6 図書館はどこへ向かうのか 8.3 読者と読書 8.3.1 読者 8.3.2 読書の定義、対象、形態 8.3.3 読書の実態 8.3.4 読書への誘い 日本出版学会 編 発行元:印刷学会出版部 A5判 256ページ
-

活版印刷人 ドラードの生涯 リスボン→長崎 天正遣欧使節の活版印刷
¥2,200
発行:2017年9月 南蛮船で来て南蛮船で消えた日本最初の活版印刷。 天正少年遣欧使節の従者として活版印刷術を西洋に学び、日本に伝えたコンスタンチノ・ドラードの生涯を、著者が実際に国内外のゆかりの地を訪れ、丹念に掘り起こした。 日本の印刷文化史のなかで重要な役割を果たしたにもかかわらず、これまでほとんど注目されることがなかったドラードの実像に迫る。 【本書は、初版第二刷をもとにオンデマンド印刷(POD)により製作してあります】 ●主な内容 ヴァリニャーノとの出会い 使節の計画 ゴアで見た印刷 南蛮大王の図書室 マルチノの演説 キリシタン版の印刷 ロドリゲスの文典 ほか 青山敦夫著 発行元:印刷学会出版部 四六判 248ページ
-
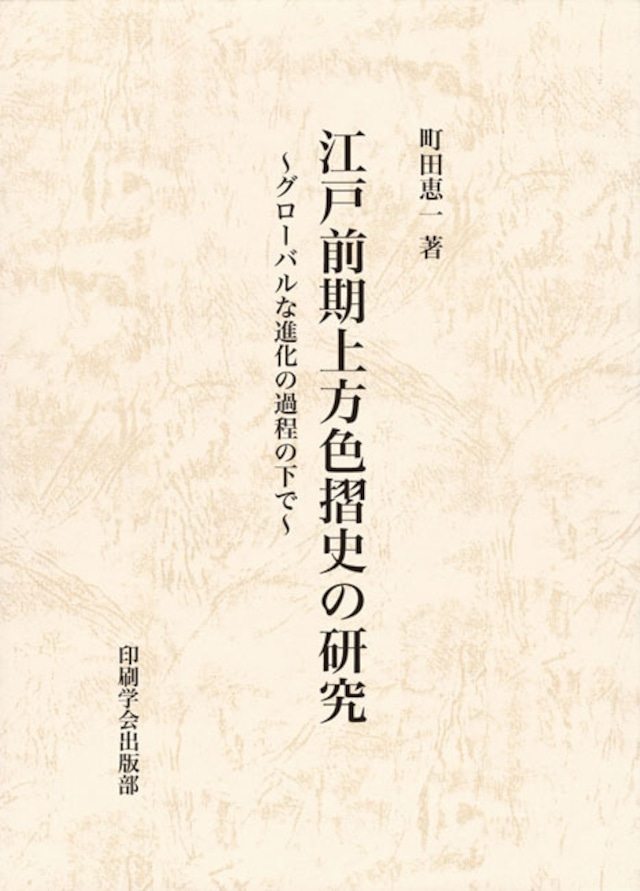
江戸前期上方色摺史の研究 ~グローバルな進化の過程の下で~
¥30,800
発行:2017年5月 日本の印刷術伝来から、江戸時代に浮世絵など華麗な美術作品として色摺り印刷物が花開くまでの道程を、政治や宗教、出版文化など、社会的・技術的背景から考察した印刷・出版技術史。 また紙の発生と進化、及び、世界の印刷技術についてまで言及し、グローバルな視点で印刷技術がどのように進化し、伝播していったかについて検証していく。 ―主な内容― 第一章 切支丹来朝と角倉(吉田)氏 Ⅰ切支丹時代の幕開け―教育と切支丹の開版事業 Ⅱ我が国に於ける色摺版本の濫觴『塵劫記』と吉田光由 第二章 江戸前期上方色摺版本の系譜 Ⅰ吉田光由以後の色摺版本 Ⅱ上方開版(彫、摺)江戸販売の色摺俳書 Ⅲ一枚摺 紅摺絵への始動 第三章 紙及び印刷術の発明と進化 Ⅰ紙の発明と進化 Ⅱ印刷術 編著者: 町田恵一(国際浮世絵学会 理事) 発行元:印刷学会出版部 B5判(上製/函付) 328ページ (カラー56ページ + モノクロ272ページ)
-

「未来への画像」 千葉大学画像系学科100周年記念誌
¥4,400
発行:2016年10月 1915年(大正4年)画像系学科の前身の設立から、現在にいたる学科、研究室の動向までの100年のあゆみを、史実および同窓会員、教職員の寄稿で紹介。 目次 世界に輝く未来志向型総合大学へ 徳久剛史 情報工学と未来への画像 関屋雄大 千葉大100周年、おめでとうございます。 湯本好英 1章 100年のあゆみ 東京高等工芸学校前史 1.百周年の起点 2.製版科の前史 3.臨時写真科の前史 4.東京高等工芸学校の設立 5.校名が東京工業専門学校となる 2章 100年のあゆみ 国立大学として 1.千葉大学の創設 2.工芸学部から工学部に 3.千葉大学工業短期大学部 4.写真印刷工学科 5.工学部と工業短期大学部が西千葉校舎に移転 6.工業短期大学部から工学部特設工学課程へ 7.大学院工学研究科に写真および印刷工学印刷工学専攻設置 3章 100年のあゆみ 画像工学科へ 1.画像工学科の誕生 2.画像工学科と特設工学科課程画像応用工学専攻との一体化 3.画像工学科、画像応用工学科への分離 4.大学院自然科学総合研究科(博士課程)の誕生 5.画像工学科と画像応用工学科の再合体:新画像工学科の誕生 6.情報画像工学科の誕生 4章 100年のあゆみ 国立大学法人、そして未来へ 1.融合科学研究科の設立と大学院の部局化 2.情報画像工学科から画像科学科、情報画像学科へ 3.千葉大学らしい画像を 5章 画像と大学・同窓会 6章 画像と産業 千葉大学工学部画像系学科のあゆみ 寄付者一覧 編集:印刷学会出版部 発行元:千葉大学画像工学同窓会 A4判 122ページ
-

電子書籍は本の夢を見るか -本の未来と印刷の行方-
¥1,760
(発行:2015年2月) 20年前には夢物語だったSF・近未来の世界がついにやってきた。 スマートフォン、タブレットPC、TV会議、バーチャルアイドル、電子書籍―…。 高速インターネットで、便利に豊かに回る社会。 その一方で、二千年以上人間とともにあり、その文化の根幹を形づくってきた「本」の存在が揺らいでいる。 本の歴史とICT技術の発展の、双方を見つめ続けてきた著者が、老舗印刷会社の経営者として、研究者として、パソコンマニアとして、父親として、愛読書家として、「本」と印刷、そして情報化社会を生きる人間の今と未来を語る。 ●目次 第一章 人間と本 「本」ってなに 大震災の少年ジャンプ 三代の文学全集 二年目の電子書籍抵抗勢力 本を処分する 本の解剖学 紙の復権 第二章 コンピュータで情報を読む デジタル時代の本のかたち CD-ROMの登場 すべてはインターネットへ そして電子書籍 電子書籍の作り方 電子書籍で『我、電子書籍の抵抗勢力たらんと欲す』を出す iPadブーム iPadの実用性 画面は横長、紙面は縦長 電子書籍と明朝体 電子マンガの次巻はまだか 日本語オンラインジャーナルを目指して PDFではなぜだめか 若旦那の電子書籍二年 電子出版EXPOに見る印刷屋の未来 第三章 インターネットと人間 ICTで便利な世の中 日曜研究者はネットで 今日からスマホ 次はフェイスブック 四年目のパソコン ベッドサイドのタブレット交替 どこでもコンピュータ 大人になったIT少年 スカイプでTV会議 かみたのみの終焉 電子式年遷宮挙行 方眼紙エクセル 初音ミクを知っていますか 第四章 本の未来をめぐる攻防 本づくりの歴史 私は印刷業を生業とする家に生まれた 活版の時代 写植とモノタイプ 月面着陸と電子組版 私の個人的体験 電算写植からさらにDTP、電子書籍へ 活版博物館から モノタイプを知っていますか 寅さんとタコ社長 マッキントッシュ三〇年 IVSで漢字コード問題は終わるか CTP三代目 オフセットの搬出 ドルッパへ行こう 印刷機メーカーさんへ 本はまず機械が読む たかが名刺されど名刺 「紙の」校正 卵の殻 業態変革という名の空中戦 私が前進しているのである 中西秀彦著 発行元:印刷学会出版部 四六判 216ページ
-

出版研究54
¥2,860
発売:2024年6月20日 出版に関する事項の調査、研究活動を行う日本出版学会の会員による、出版・情報・メディアなど多様な分野の研究論文や有識者の座談会を掲載。 目次 特集 国際出版研究フォーラムと東アジアの出版研究 巻頭言 国際出版研究フォーラム 開催概要一覧 ―第1回(1984年)~第20回(2022年) 座談会 国際出版研究フォーラムの歩みと今後の展望 日本と中国における出版研究の動向分析 ―戦後から2000年代までの出版関係書籍を対象として 伊藤民雄 韓国における出版研究の傾向に関する研究 ―学位論文と韓国出版学会の学術論文を中心として 金 貞明 ■ 論文 異境から〈秘境〉へ ―南洋一郎の冒険小説に見る戦後の改訂作業をめぐって 大道晴香 デジタル化にともなう雑誌概念の変容とその統制 清水一彦 学協会誌をJIS X 23761に適合するEPUB出版物として刊行するうえでの課題 ―『出版研究』を事例に 植村要,池下花恵,鷹野凌,徳永修,梶原治樹,矢口博之 執筆者紹介 日本出版学会の活動と組織(2022年度) 日本出版学会会員規定 『出版研究』投稿規定 『出版研究』査読方法および審査基準 日本出版学会会員著作執筆目録(2023年1月~2023年12月) 日本出版学会会員名簿 日本出版学会 編集 発行元:日本出版学会 A5判 200ページ
-

「井上嘉瑞と活版印刷」著述編
¥1,760
発行:2005年4月 嘉瑞工房創立者である井上嘉瑞氏の著述と組版作品を2分冊で復刻。活版印刷が消え去ろうとしている時代に、あらためてその工芸的な価値が注目されている。そこで、戦前から戦後にかけて井上氏が著した活版印刷、とくに欧文組版におけるタイポグラフィについての思想と実作品を通して、現在の組版意識の高揚を図る。 ※作品集の底本である小冊子は,一般販売を想定した物ではなく,著者の知人に進呈するためにそれぞれ50〜100部程度活版印刷で作られたもので,組版・タイポグラフィの美しさだけではなく,資料的価値も高い。 ●主な内容 井上嘉瑞の人と作品(解説:高岡昌生)/ 田舎臭い日本の欧文印刷/工房雑語 ほか 井上嘉瑞 著 発行元:印刷学会出版部 A6判・上製本 110ページ
-

紙と印刷の文化録 ―記憶と書物を担うもの―
¥4,180
発行:2012年2月 本格的な電子書籍の攻勢を前に、果たして紙は生き残れるのか? 紙を専門に研究してきた筆者がその時々に興味を持った時事問題や社会情勢にも触れ、好評を得た月刊『印刷雑誌』の連載「わたしの印刷手帳」を一冊にまとめた。本書は、紙の用途の一つであるメディアを中心にその応用分野の紙と印刷の歴史や技術から経済まで幅広い内容で構成される。好奇心旺盛な著者の視点が時に鋭く、時に温かく紙の行く末を見つめた。 ●主な内容 メディアとしての文化の対比/WikiLeaks問題が再認識させた印刷物の価値/紙の進歩とは何か/無文字文化と歴史の推定/認知科学から見た電子書籍の可能性/印刷における「用と美」/印刷の未来は予測可能か ほか 尾鍋史彦 著 発行元:印刷学会出版部 四六判 上製 288ページ 日本図書館協会選定図書
-
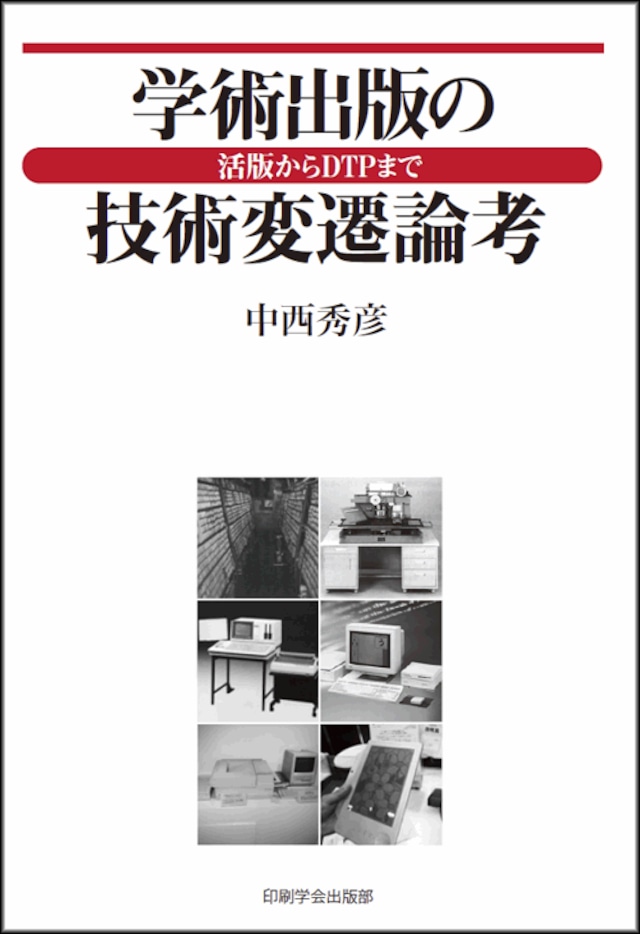
学術出版の技術変遷論考 ―活版からDTPまで―
¥7,480
発行:2012年2月 日本の学術出版を支え続ける印刷組版の技術は、より早く、より正確に伝えることを目指し科学技術の進歩と共に活字組版から写真植字、DTPへと変遷してきた。しかしその変遷には、多くの技術的困難を伴ってきた。本書はそんな学術出版印刷を京都で100年以上支える印刷会社の知られざる舞台裏を詳細に記録した技術変遷史でもある。人文科学系の多言語組版も得意とする同社をモデルとして、知の集積を支える印刷技術の課題を考察した。学術出版の研究や大学、図書館の研究書として。 ●目次 序章:本書の目的と構成 第1章:学術印刷の変遷 第2章:活版と写植の時代 第3章:電算写植の時代 第4章:電算写植の時代2 第5章:DTPの時代 第6章:学術出版技術変遷論考 終章:学術出版印刷の新地平 中西秀彦 著 発行元:印刷学会出版部 A5判・上製本 450ページ
-
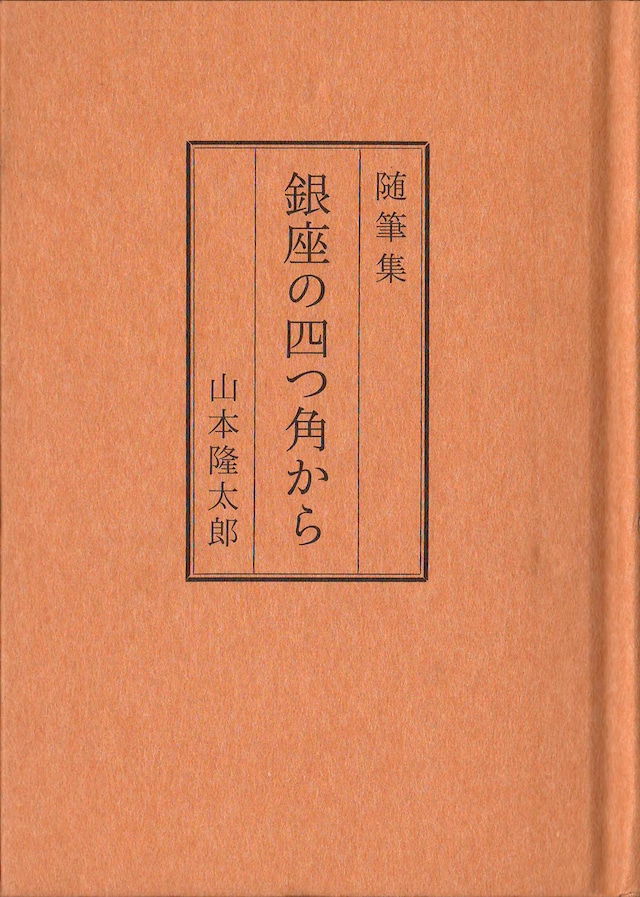
随筆集『銀座の四つ角から』
¥2,200
発行:2005年10月 1980年から2000年までの20年間にわたり、月刊紙『新聞技報』に連載した新聞、印刷にまつわるエッセイ「銀座の四角から」から69編を選び収録。新聞・印刷の技術紹介あり、テレビ出演時の愉快なエピソードあり、時には業界への手厳しい提言や含蓄のある社会風刺、そしてお色気も少々。著者の軽妙洒脱な語り口をぜひお楽しみあれ。 ●主な内容 小樽新聞社/一番汚い話/若い女性の好き嫌い/年末年始のマスコミ/天皇の戦争責任/明朝体のウロコ/読売と中公/印刷と出版と編集権/活字と文豪/印刷表現のむつかしさ ほか 山本隆太郎 著 発行元:印刷学会出版部 A6判・上製本 264ページ
-

随筆集『続・銀座の四つ角から』
¥2,200
発行:2008年7月 半世紀以上にわたり印刷業界を見続けてきた著者。本書では、ここ数年に著者が体験した出来事や、かつて経験した戦争の思い出、通い親しんだ銀座の街並みとそこに構える店の移ろい、印刷業界でこれまでに巡り会った様々な人たちの回顧録など、豊富な話題66編をユーモアやペーソスで綴った。 ●主な内容 ある探偵事件の話/うれしかった一言/書道と留学生/香のはなし/木版刷りの音楽教科書/赤面する/文豪とネコ/休日/真夏座とこまつ座/戦争の犠牲者/琴平水心隊/キスの話/東京で会えた父/銀座の食巡り/出版記念会/安藤七宝店と銀座の街/従業員教育/石版再考/読むと手が汚れた新聞/美人ポスター展/特殊印刷/付き合い/江戸人の再来,横山芳郎/約束/人間万事塞翁が馬 ほか 山本隆太郎 著 発行元:印刷学会出版部 A6判・上製本 176ページ
-

『印刷雑誌』とその時代 ―実況・印刷の近現代史―
¥9,460
発行:2007年12月 明治24(1891)年創刊の初代と現在まで続く大正7(1918)年創刊の2代目を合わせ、117年にわたり日本の印刷文化・技術の変遷を見つめ続けてきた印刷専門誌『印刷雑誌』。本書は、その雑誌記事を通して、日本の近現代印刷史を通覧しようというものである。第1部では、印刷と社会、印刷技術、タイポグラフィなど各ジャンルごとに、監修者による解説を収録。第2部では、これまでに収録した膨大な記事の中から、今読んでも興味深く、かつ資料的価値のある記事を集成、当時の印刷人が同時代を記した臨場感溢れる掲載記事を年代順に掲載し、日本の急速な近代化を追体験できるような構成を採った。 《 正誤表→http://www.japanprinter.co.jp/mediabooks/jidaiseigo.pdf 》 ●主な内容 第1部 近代印刷史歴覧 第1章 近代日本と印刷文化/第2章 印刷技術の変遷/第3章 カラー印刷の一世紀/第4章 技術とデザイン/第5章 組版、欧文タイポグラフィ/第2部 『印刷雑誌』記事集成 第1章 初代『印刷雑誌』の時代/第2章 『印刷雑誌』創刊のころ/第3章 戦争と印刷/第4章 戦後復興期/第5章 高度成長期/第6章 バブル経済と失われた十年/第7章 IT時代の印刷 中原雄太郎,松根格,平野武利,川畑直道,高岡重蔵,高岡昌生 監修 編集・発行元:印刷学会出版部 A5判・上製本 824ページ 日本出版学会特別賞受賞
-

活版印刷紀行 キリシタン印刷街道/明治の印刷地図
¥1,980
時は平成、日本の活版印刷ゆかりの地をめぐる旅。 最初は天正少年使節によって島原の加津佐でスタート。 二度目は明治の印刷誕生の地、長崎が出発点。 活版印刷誕生の地を訪ねて著者が見たものは聞いたものは。 ●主な内容 日本最初の印刷技術者/活版印刷の聖地天辺の丘/活字も人もみな消えた/キリシタン印刷街道の終点/本木昌造とお諏訪さん/居留置文化と印刷/印刷は銀座から ほか 青山敦夫 著 発行元:印刷学会出版部 四六判 232ページ
-

印刷の父 グーテンベルク
¥8,800
世界で最初に金属活字によって印刷された42行聖書(複製を添付)は185部。生地マインツを追放され、異郷の地で印刷術を成した生涯とその情念を、長年の調査と独自の視点により綴った力作。 ●主な内容 ストラスブール1428~1446活字と印刷機/マインツ1446~1468印刷された聖書 メアリー・E・ゲクラー 著 浅田清節 訳 発行元:印刷学会出版部 A5変形判 320ページ 残部僅少,美本なし
-

活字よ、 ― 本木昌造の生涯 ―
¥1,650
SOLD OUT
発行年:1984年 長崎奉行配下のオランダ通訳、活字に魅せられた異色の幕末人、本木昌造。 動乱と文明開化の世情の中で、活字をつくり、印刷することに情熱を傾けた男の軌跡。 桐生悠三 著 発行元:印刷学会出版部 四六判上製 229ページ
-

銀行券にみる近現代世界の国々
¥1,650
各国の威厳や誇りが表現されることが多い銀行券や政府紙幣、そのデザインには国のイメージを内外に伝えるという作用があります。 本書ではそのデザインや特徴から、込められたメッセージや国に関する発行当時の情報を引き出し、世界各国の歴史や情勢をひも解いていきます。 ●目次 第一章 日本の銀行券の変遷 第二章 北朝鮮の通貨改革と政治経済情勢 第三章 中国人民幣がたどった歴史と銀行券のデザイン 第四章 台湾、香港、マカオにおける社会と通貨の変遷 第五章 アジア諸国の特色が表現された銀行券 第六章 アフリカの通貨にみる強権政治 第七章 多彩な英国の歴史と通貨 第八章 北大西洋島嶼の歴史と通貨 第九章 米ドルの歴史と銀行券のデザイン 第十章 ソ連、ロシアの政治経済の変遷と多様な通貨 第十一章 第二次世界大戦後の世界と通貨 冨田昌宏 著 発行元:(財)印刷朝陽会 販売:印刷学会出版部 A5判 215ページ
-

図説 印刷文化の原点 ―The Starting Point of Printing Culture―
¥1,650
日本で「印刷」という言葉は一部の人達の間で既に幕末に使われていた。 『LIFE』誌が「過去千年間で最も大きな出来事」として「グーテンベルクによる聖書の印刷」をトップに選出したように、印刷が文化と深く関わりがあるものならば「印刷」という言葉、歴史、教育の原点を知る必要があるのではないだろうか。 印刷研究家である著者が、日本文化における印刷の起源を探る。印刷に関わる全ての方にお薦めします! ●目次 第一章 過去千年間で最も大きな出来事 第二章 日本語による新聞の始まりとその時代 第三章 印刷という用語の始まり 第四章 百万塔陀羅尼・国宝の印刷物・その他 第五章 日本における印刷教育の源流 ほか 松浦広 著 発行元:(財)印刷朝陽会 販売:印刷学会出版部 A5判 148ページ 日本図書館協会選定図書
-

分かりやすくて面白い 切手印刷のはなし
¥770
最近の世界各国における切手は、従来からの伝統的なグラビア、オフセット、凹版印刷などの印刷技法のほかに、いろいろ変った印刷方式や加工技術を用いた変わり種切手が増加しています。本書は、これらの新しい技術などを用いた珍しい切手を、その製造技術も混えて紹介します。 ●目次 1.一般に使われている切手の印刷技法 2.珍しい切手の印刷や加工技法 植村峻 著 発行元:(財)印刷朝陽会 販売:印刷学会出版部 B5判 55ページ
-

かな活字の誕生 ―外国人の作った金属かな活字―
¥1,650
SOLD OUT
1800年代、海外では日本への関心が高まり、東洋学者の指導で外国人の手による「かな活字」が作られていた。明治初期にかけて多く作られた外国人の日本語活字とは、どのようなものだったのか?多彩な資料を元に年代を追って考察していく。 ●主な内容 カタカナ:1818年(仏)/1832年(独)/1847年(墺)/1847年(米)/1854年(仏)/1855年(蘭)/1858年(仏)/1865年(仏)/1867年(米),ひらかな:1600年(日)/1847年(墺)/1854年(仏)/1857年(蘭)/1871年(仏)/1874年(米) ほか 板倉雅宣 著 発行元:(財)印刷朝陽会 販売:印刷学会出版部 B5判 160ページ
-

印刷よもやま話 ―印刷技術の歴史―
¥1,650
SOLD OUT
「印刷」の歴史と技術について、その起源から今日にいたるまでの興味深い話題をカラー図版とともに解説。印刷とその周辺の歴史をダイジェストで紹介する。 目次/他 ●主な内容 絵のはじまり/書写材料の歴史/木版印刷/紙幣の歴史/活版印刷機の発展/写真/グラビア印刷の発明/フォトレジストとPS版/水なし平版/カラースキャナとCEPS/印刷のデジタル化/オンデマンド印刷機/精密電子部品 ほか 吉島重朝 著 発行元:(財)印刷朝陽会 販売:印刷学会出版部 B5判 92ページ
-

教科書にみる印刷術の歴史
¥1,572
SOLD OUT
【美本なし(表紙に若干の傷・日焼けがあります)】 戦前から戦後にかけての教科書に記載された記録や、その教科書自体の製本方法から、印刷術の変遷を眺める。時代は木版、石版、銅版の時代を経て、本木昌造の活版伝習所によって鋳造活字製法が広まり活版印刷が盛んになっていく。さらにはそれと並行して移り変わる新聞印刷の歴史に至るまでを、それぞれの時代を反映した学校教育の中における印刷術という視点から見つめ直す一冊。印刷機械や印刷風景を描いた挿絵など、理解を助ける図版も23点収録した。 ●主な内容 戦前の教科書(活版と木版,印刷術の効用,新聞売り,銅版,本木昌造,印刷の歴史,新聞,製紙,廃物利用)/戦後の教科書(活字の字体,活字の発明,印刷工場見学,書物の発達,印刷術の進歩と文明,新聞の歴史,ジョセフ・ヒコ,フランクリンと印刷)ほか 板倉雅宣 著 発行元:(財)印刷朝陽会 販売:印刷学会出版部 A5判 181ページ
-

お札のはなし ―その歴史、肖像と技術―
¥1,650
SOLD OUT
貨幣経済の中で常に身の回りに存在しているお札。高度な偽造防止対策など、その印刷技術は江戸時代から現代に至るまで様々な変遷の歴史をたどってきた。日本や世界のお札とその印刷技術、肖像にまつわる話やにせ札の見分け方など、全ページカラーでわかりやすく解説する。 ●主な内容 お金、お札の登場/日本のお札の歴史/日本のお札の肖像/世界のお札の肖像/印刷術の変遷/お札の製造工程/にせ札の見分け方/世界のお札の特徴/世界の珍しいお札/お札の話題いろいろ ほか 植村峻 著 発行元:(財)印刷朝陽会 販売:印刷学会出版部 A4判 112ページ
